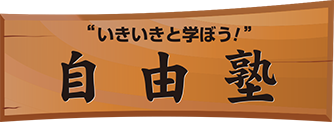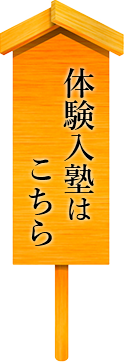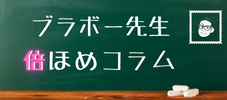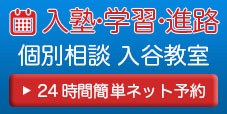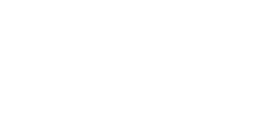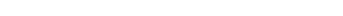- 【秋から始める私立中学受験について考える】すでに大手進学塾に通っている方、これから始めようと思っている方必見です!
- 2022. 10. 6/入谷教室のブログ日暮里教室のブログ
- 自由塾代表の中島です。中学受験の準備は早い方が…というお声をよく耳にしますし、そのような相談もよく受けます。特にその開始時期については、春先の2月、3月でないと…と思い込んでいる方も少なくないように感じます。確かにその時期、たくさんの塾のチラシ、その他の広告が溢れ、そのタイミングを逃すともう手遅れと思ってしまうケースもあるようです。でも決してそんなことはありません。むしろ年度替わりで何かと変化の多い春先より、秋のこの時期こそ腰を据えて新たなスタートを切れる生徒も少なくありません。では、いくつかのケースに分けて、秋から始める中学受験についてのモデルケースや、お勧めの学校のご提案です。焦らなくても、お子様に合った学校は必ず見つかります。【すでに大手の学習塾に通っている場合】春から大手進学塾に通い始めたものの、以下のようなケースでお悩みということはありませんか?●一斉授業についていけなくて、やる気を失いつつある●宿題が多すぎたり、拘束時間が長すぎたりで、疲れ気味●勉強自体が嫌いになるのでは?と不安思い当たる場合、一度学習法や学習スタイルを見直すべき時期です。そして、志望校についても再検討する必要があります。いつかやる気になるのでは…?で、ずるずるは、取り返しのつかない場合も少なくありません。自由塾にご相談いただき、方向転換をして中学受験された方のブログです。↓【4年生の秋から始める場合】まだ、時間的に少し余裕があります。まず、焦らず足元を見つめることから始めましょう!(4年の秋からでしたら、学校の選択肢も少なくありません。)具体的には、現状の理解度や、受験に対するモチベーションの確認からです。また、4教科受験でいくのか、2教科受験でいくのかの確認も。この時期ならまだ4教科でも間に合います。でも理社があまり好きでないお子様は2教科にしぼった方が好結果が望まれます。そのあたりのご相談から始めさせていただきます。その上で、これから春までの数カ月をこれまで理解できていなかったことの復習や受験に向けての態勢作りに当てることができます。最初から、ガンガン詰め込むようなことはせず、まずお子様やご家庭とコミュニケーションをとることで、受験に向けての環境を整えるのが、自由塾の寺子屋スタイルです。●4年生の秋から受験対策を始める場合の自由塾おススメのプラン①4教科受験(国算理社)の場合最低週3回の通塾(1回110分)②2教科受験(国算)の場合最低週2回の通塾(1回110分)※このプランで目指すおススメの私立中学駒込中学 安田学園中学 開智日本橋中学 郁文館中学 獨協埼玉中学(ここ数年で自由塾の塾生が合格した学校やお付き合いのある学校です。すべて網羅しているわけではありません。)【5年生の秋から始める場合】「5年生の秋からでは、もう間に合わない⁉」そう思い込んでいる方も少なくないでしょう。何度も言いますが、そんなことはありません。まず、どういった学校を目標にするのか。現状どれぐらいの理解状況か。それを把握するところから自由塾の指導は始まります。この時期のスタートであれば2教科受験の方が無難ではあります。でも国語、算数のどちらかが苦手だったり、逆に理科、社会が得意な場合は4教科も検討したいところです。まずは態勢作りから。その上で、生徒個々にゴールまでの学習プランを作ります。●5年生の秋から受験対策を始める場合の自由塾おススメの プラン①2教科受験(国算)の場合最低週3回の通塾(1回110分)②4教科受験(国算理社)の場合最低週4回の通塾(1回110分)※このプランで目指すおススメの私立中学は…京華中学 京華女子中学 桜丘中学 サレジアン国際学園中学 足立学園中学 芝国際中学(ここ数年で自由塾の塾生が合格した学校やお付き合いのある学校です。すべて網羅しているわけではありません。)【英語受験、英語利用受験の場合】このところ、一気に増えてきた英語利用受験。形態は英語そのものの試験を課す学校と英検の指定級取得で加点となる学校があります。試験の場合、英語のみの学校と国語、算数2科または算数のみが加わる学校があります。英検をすでに取得している、英語が得意、英語が好き、そんな方にはお勧めの受験方法です。●英語利用受験の場合のおススメのプラン最低週3回(+算数のみの場合は週2回)の通塾(小学生英語・英検対策コースまたは英語チュートリアルコース+国語・算数各1回110分)※このプランで目指すおススメの私立中学は…順天中学 駒込中学 京華中学 京華女子中学 桜丘中学(ここ数年で自由塾の塾生が合格した学校やお付き合いのある学校です。すべて網羅しているわけではありません。)●英語受験(英語のみ)の場合のおススメのプラン最低週1回の通塾(小学生英語・英検対策コースまたは英語チュートリアルコース)※このプランで目指すおススメの私立中学は…サレジアン国際中学(インターナショナルadvanced) 聖学院中学 女子聖学院中学(ここ数年で自由塾の塾生が合格した学校やお付き合いのある学校です。すべて網羅しているわけではありません。)★自由塾のいきいき私立中受験コースでは
●生徒ひとりひとりの志望校や理解状況に応じて、最適のカリキュラム、テキストで指導します。
●各生徒に合わせて、難しすぎる問題や単なる詰込みは除外し、無理なくムダなく指導します。
●お子様に合った私立中受験を学校選びからお手伝いします。
●一人一人の生徒に寄り添い、ゴールまでの道筋を共に考え、共に歩むのが自由塾の寺子屋スタイルです!
★集団指導ではなく、個別指導で中学受験勉強をするメリットとは?
●集団指導でありがちな、わからないまま先に進んだり、「そんなのわかってるよ」といったことを何度も繰り返したりといったことがなく、自分のペースや理解状況に合わせて効率的に学習することができます。
●集団指導では質問ができない生徒でも、気軽に先生に質問することができます。
●苦手単元や弱点を集中的に学習することができます。また、入試直前には自分の受験する学校の過去問を中心に学習することもできます。
★まずはお気軽にご相談から
「いつから始めればいいの?「」
「どんな学校を選べばいいの?」
「2教科、4教科どちらがいいの?」
「今のままで大丈夫??」
中学受験への悩みや迷いは尽きませんね。
どんなことでもお気軽にご相談ください。熱意と誠意をもって対応させていただきます。
「いきいきと学ぼう!」
自由塾代表 中島正浩
ご相談はこちらから↓
入谷教室
入谷教室のページを見る > フォームからお問い合わせする 面談予約をする日暮里教室
日暮里教室のページを見る > フォームからお問い合わせする 面談予約をする
- 【中1、中2対象】2学期の学習内容はこんなに大事! 英語、数学のここがポイント!
- 2022. 9. 29/入谷教室のブログ日暮里教室のブログ
- 自由塾代表の中島です。多くの区立中学では、9月末から10月上旬にかけて中間テストが行われています。一方、2学期は学校行事も多く、子供たちにとっては何かと落ち着かない時期でもあります。お子様のテスト勉強の様子、そして肝心のテスト結果はいかがでしょうか?2学期の学習は、受験を控えた中3生はもちろんですが、中1、中2の生徒にとっても実はとても大切なのです。その理由のひとつは英語、数学の内容が1学期に比べて格段に難しくなるからです。そして、高校入試にも直結する内容も、かなり多いのです。学年・教科ごとに見てみましょう。まず2学期中間テストまでの学習内容は・・・(学校によって、多少の進度の差はあります。)【中1英語】●三単現のSやその疑問文、否定文の作り方、進行形すでにbe動詞と一般動詞で混乱しているところに追い打ちのように、これです。昨年の教科書改訂により文法事項をひとつひとつ整理して丁寧に学習する機会が、中学校でも著しく減っています。英語ってよくわからないという生徒が、ここから一気に増えることは昨年の経験からも間違いありません。中3になってから、be動詞?一般動詞?三単現のSって??とならないよう(実際中3になってから塾に来る生徒でこのような生徒は少なくありません)今のうちに確実に理解しておくことが大切です。【中2英語】●不定詞、動名詞いずれも都立高でも私立高でも入試で確実に問われるところです。また、長文問題でも当たり前のように出てくる文法事項なので、その使い方、意味をしっかり理解する必要があります。さらに、これも教科書改訂の影響で、特に中2になると教科書に出てくる単語が質量ともにかなり手応えのあるものとなります。これを疎かにしていると、高校入試の長文はまず読めません。【中1数学】●方程式の計算、方程式の文章題方程式の計算は高校入試で、必出です。受験者全体の正答率が高いので、ここで点数を落とすことはできません。また、その計算ができないと、これから教わる関数や図形の問題でもそれを利用して答えを導く問題が多いので、解くことができません。方程式の文章題は都立高校入試では直接出ることはまずありませんが、私立高校では論理的思考力を見るため、好んで出す学校も少なくありません。【中2数学】●連立方程式、一次関数いずれも高校入試では避けて通れない単元です。連立方程式の計算問題は高校入試では頻出です。また、関数や図形の問題でもこれができないと解けない問題も出てきます。一方、一次関数は、数学を学ぶ上でひとつの鬼門ですね。ここで数学につまずく生徒達を数多く見てきました。この一次関数は都立高校入試でも隔年で大問としてかなりの配点で(15点程度)出されます。確実に理解しておくべき単元なのです。以上、今学習している内容がいかに高校入試に直結しているか、少しご理解いただけたでしょうか?自由塾では、基本的に今学校で教わっている内容をしっかり理解することをメインに授業を進めます。但し、上記のような重要な内容については適宜、繰り返し復習し定着を図ります。また、冬期講習では特に、上記の内容について徹底して復習をし、高校入試に向けての足場をしっかり固めていきます。では、これから2学期期末テストまでの学習内容は?【中1英語】●過去形ここでもまた、ぐっとハードルが上がります。規則動詞、不規則動詞の区別、不規則動詞の活用など、今のうちにしっかり理解しておかなければならないことばかりです。このあたりで混乱すると、後から取り返すのが大変になってきます。【中2英語】●助動詞、比較など助動詞は覚えるべきことがたくさんありますし、高校入試で扱われる会話文や長文でも頻出です。ここを読み違えると、選択問題でも正解に到りません。比較は特に私立高校入試の文法問題で好んで出題されます。【中1数学】●比例、反比例比例が理解できていないと、中2で習う一次関数はまず理解できません。そして前述したように一次関数は高校入試で最重要単元の一つです。【中2数学】●平行線と角、合同の証明角度を求める問題は都立でも私立でも高校入試の小問で頻出です。確実に得点したいところです。そして何と言ってもここは合同の証明がメインとなります。都立高校入試ではこの合同の証明か相似の証明かが必ず出されます。配点も高いです(7点程度)。全くわからないから、手をつけず白紙で出すということのないようにしなければなりません。このように中間テスト後も大切な単元が英語、数学ともに目白押しです。自由塾では前述しましたように、まず学校の学習内容をしっかり理解し、中1、中2のこの時期は、次回期末で結果を出すことに重点を置いて指導します。それが高校入試につながっていくからです。さて、ここまでお読みいただいた上で、改めてお子さまの中間テストの答案用紙を見ていただきたいのです。単に点数より、これまで挙げてきたような内容が、理解できているのかいないのか、肝心なのはそこです。「本当に基礎がわかっているのか?」「家庭学習はどうすればいいのか?」「このままで高校受験は大丈夫なのか?」自由塾では、そのようなご相談も随時お受けしています。中間テストの問題と答案を持って、お気軽にご相談いただければと思います。入塾を無理に勧めるようなことはいたしません。どんなご相談でも親身に対応させていただきます。「いきいきと学ぼう!」自由塾代表 中島正浩
- 夏期講習スタート!
- 2022. 7. 28/入谷教室のブログ日暮里教室のブログ
- 自由塾代表の中島です。自由塾入谷教室、自由塾日暮里教室では7/25(月)より夏期講習がスタート!お陰様で連日盛況。感染対策にも神経を割きながらですが、熱気ある講習が展開されています。私たちの求める理想の夏期講習は●もちろん、まずしっかり成果につなげること!「暑い中通ってくれる生徒達に、必ずやしっかりした夏の成果を残したい。」という強い思いがあります。そして、もう一つ●せっかくの夏休み、わざわざ通ってくれるのだから、「来てよかった!」「楽しかった!」と思って帰ってもらうこと!だから緊張感の中にも、時に明るい笑い声も聞こえてくるのです。「明るく活気に満ちた夏期講習」それが私たちの目指すところです。Ⅰ期目の今週は、受験学年、受験クラスのみの講習です。そして、同時に全生徒対象の「学力点検テスト」も実施しています。その結果をもとに、来週のⅡ期目からは全生徒対象の講習が本格スタートします。講習と学力テストの二本立てで、ハードなスタートですが、まだまだこれから。明日からもがんばります!「いきいきと学ぼう!」自由塾代表 中島正浩
教室ページはこちら
入谷教室のページを見る > 日暮里教室のページを見る >
- 「まだ間に合う!夏期講習」中1、中2、非受験の小学生は8/1㈪スタート! 7月中の無料授業でお試しください。
- 2022. 7. 15/入谷教室のブログ日暮里教室のブログ
- 自由塾代表の中島です。夏休みが迫ってきました。自由塾入谷教室、日暮里教室でも7/25㈪から夏期講習が始まります。でもこれ、受験学年、受験クラスに限った話。中1、中2や中学受験しない小学生は8/1㈪からのスタートです。「今からではもう遅い。」とあきらめていませんでしたか?確かにクラスや時間帯によっては、お断りせざるを得ないところもあるのですが、まずはご相談ください。さらに、今お申込みいただけば、7月中の通常授業を無料で受講いただくことができます。夏期講習がスタートする前に、自由塾の教室の雰囲気や先生に慣れていただくためです。同時に私たち教える側もお子様の性格や理解状況を、講習前に把握することができます。では、肝心の夏期講習では・・・●中1、中2英語や数学がよくわからないという生徒が増えています。確かに教科書の内容も定期テストの問題も難しくなっているのは事実。わからないと言っている生徒の多くは、まず基礎が理解できていないということが大きな要因です。英語は、be動詞、一般動詞の区別や三人称単数からひとつひとつ整理しながら丁寧に指導します。数学は、まず正負の数や文字式から、もっと遡って分数計算から指導する場合もあります。●小5、小6割合や速さ、分数の計算理解できていますか?これらは中学の数学でも使う大切な単元です。夏期講習で特に重点的に指導します。国語の長文読解は毎日、説明文、物語文、随筆などいろいろなジャンルの文章を読み解くことにより、読解のコツをつかみます。中学英語に備えた小学生の英語クラスもあります。ご相談ください。●小学2〜4年漢字の読み書きや計算などの基本学習を毎日少しずつ、コツコツ学習します。また、国語の読解や記述問題、算数の文章題にもチャレンジします。また、毎日短い時間でも集中して机に向かう習慣を育みます。★まずはご相談から。自由塾は決して敷居の高い学び舎ではありません。どんなことでもお気軽にどうぞ!「いきいきと学ぼう!」自由塾代表 中島正浩夏期講習の資料請求・お問い合わせ「夏期入門講座」のお申し込みは下記ボタンから
- 「中1、中2の英語、数学が危うい。」期末テストの結果だけで責めないで! ~挽回する最大のチャンスは夏休みです!
- 2022. 7. 7/入谷教室のブログ日暮里教室のブログ
- 自由塾代表の中島です。期末テストの答案が返ってきている頃と思います。いかがでしたか?「あれっ、こんなはずでは?」と思われた保護者の方も多いのではないでしょうか。中学の定期テストは、問題がここ数年大きく様代わりしています。お父様、お母様世代のテストとは別物です。我が子の点数を見る前に、まず平均点を見てください。(学年平均50点前後という学校も少なくありません。)なかなか点数を取れず、苦戦している生徒が少なくないのです。その理由はいくつかあります。●英語・・・従来の文法中心のいわゆる受験英語から、読む、聞く、書く、話すの4技能中心に移行しようとしています。それは、長い目で見ればいいことだと思うのですが、そういった流れの中で、完全に英語から取り残されつつある生徒が増えているのも事実です。●数学・・・私たちの目から見ても、明らかに問題が難しくなっています。基本的な計算はわかっていて当然。かつ応用力や思考力を問う問題が増えている。かつ問題の分量もボリュームがあり、時間内に終わりきらない生徒も多いです。●もう一つ、各中学の定期テスト前の課題が多く、それをこなすことで精一杯の生徒が多いということも挙げられます。こんな状況ですから、ただ点数だけを見て、「何をやってるの!」「なんでこんな点数⁉」と責めるのは禁物です。ではどうすればいいのか?【英語】・中学で覚えるべき語彙数が以前の2倍になりました。語彙力の向上なくして、英語の成績は上がりません。→自由塾の夏期ステップアップ講習では、毎日の単語テストで、夏休み中に最低200語暗記にトライします。・難易度が一気に上がった文法は、系統立てて基礎からしっかり頭の中を整理することが大切です。→自由塾の夏期ステップアップ講習では、 まずはBe動詞、一般動詞から基礎を徹底的に定着させ、土台をしっかり作ります。・英語長文対策は、まず慣れることから。→日本語に変換しないスラッシュリーディングにより、速く正確に読み解くコツを伝授します。【数学】・数学はまずとにかく計算力からです。中学生でも小学校で習った分数計算が危うい生徒が実は少なくありません。→自由塾の夏期ステップアップ講習では、 計算力の土台をしっかり作ることから始めます。中2で基本計算に不安のある生徒は、その再構築から取り組みます。・関数や証明、図形など数学的思考力を問われる単元は、特に苦手意識を持った生徒が多いです。→自由塾の夏期ステップアップ講習では、 これらの単元は特に丁寧に重点的に指導し、苦手克服に努めます。・数学はわかってくると、実は楽しい教科です。その体験を少しでもこの夏にしてもらえるよう努めます。【夏期講習受講までの流れ】①期末テストの答案や問題を可能な限りお持ちください。まずはお気軽にご相談から。テスト結果をを見ながら、どういった方針で学習を進めていけばいいか、相談させていただきます。自由塾は、決して敷居の高い学び舎ではありません。どんなことでもお気軽にどうぞ!②学力点検テストを受けていただきます。(7/25〜29、希望者のみ)教科ごとの具体的な理解度を確認します。(入塾テストではありませんので、できなくても大丈夫です。いえ、できないところを確認するためのテストです。)③再度面談夏期講習でどのように学習を進めていくかを具体的に提案させていただきます。ご納得いただいた上で、夏期講習に入ります。夏休みにがんばった生徒は、例年必ず2学期から飛躍を遂げています。ひとりひとりの生徒に寄り添って成果を出す、自由塾の「全力サポート!夏期講習」。まずはお気軽にご相談ください。「いきいきと学ぼう!」自由塾代表 中島正浩夏期講習の資料請求・お問い合わせ「夏期入門講座」のお申し込みは下記ボタンから
入谷教室
入谷教室のページを見る > フォームからお問い合わせする 面談予約をする日暮里教室
日暮里教室のページを見る > フォームからお問い合わせする 面談予約をする